お使いのブラウザ(Internet Explorer)ではコンテンツが正常に表示されない可能性があります。
Microsoft Edgeのご使用をおすすめいたします。
第3回モンベル・チャレンジ・アワード 受賞記念特別対談 医師 中村哲 × モンベル代表 辰野勇
2019/12/5
モンベルクラブ会報誌『OUTWARD』2008年秋号に掲載された対談記事です。

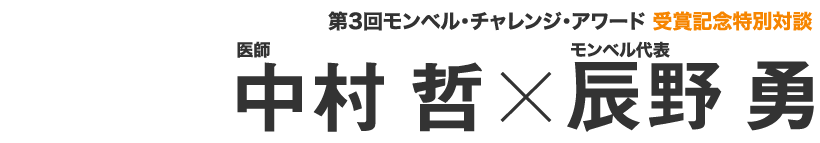
パキスタン、アフガニスタンで医療活動を中心とした現地支援に携わる中村氏。「誰もやりたがらないこそ、自分がやる―」そんな強い意志のもと、20年以上に渡り現地で奔走を続ける中村氏に、現地の様子や、その思いをうかがいました。
自然を対象に、あるいは自然を舞台として、人々に希望や勇気を与え、社会に対して前向きなメッセージを伝える活動を応援するため、2005年に創設した賞です。第3回モンベル・チャレンジ・アワードに医師の中村哲氏が受賞されました。

辰野
本誌の読者は自然が好きな方が多いものですから、中村さんがヒンズークシュに山登りに出かけたことに親しみを感じると思います。そもそもどこかの山岳会に所属していたのですか。
中村
社会人の福岡登高会。ご存知ですか。
辰野
はい。
中村
そちらの登山隊つきの医師として同行しました。
辰野
それまでも山登りは興味をもってやっていらっしゃったのですか。
中村
山登りというより、自分は虫屋といいますか…。昆虫が好きなんです。それであちこちに行っていました。
辰野
そんなつながりの中で、ヒンズークシュへのお誘いを受けられたのですね。その後日本へ戻って、もう一度パキスタンへ行かれたのは、何らかの想いを持って、機会があってのことですよね。
中村
次のきっかけは、日本キリスト教海外医療協力会がパキスタンのペシャワールへ派遣する医者を探しており、「行ってくれないか」というお話があったことです。そうしたら長くなってしまったというか…(笑)
辰野
最初は、そんなに長く行くつもりはなかったんですね。
中村
そうです。5年か、せいぜい10年もいれば、と。あそこでずっと過ごすとは思っていなかった。
自分の信心を守るイスラムの人々
辰野
何が中村さんを現地にとどめたのでしょうか。
中村
うーん、自分でもよくわからない。患者なり、仕事なりがあって、「ここでほったらかして帰るわけにはいかん」という場面があまりに多すぎたということでしょうか。
辰野
現地との信頼関係がすごくあって…。
中村
特にハンセン病の患者をたくさん診ていたので。ハンセン病は長いケアが必要な病気です。だから、自分の任期が終わったからバイバイというわけにはいかない。捨てて出て行くわけにもいかないという気持ちで、引き止められてきた面もあるでしょうね。
辰野
その後、日本からの新たな医師の派遣はなかったんでしょうか。
中村
パキスタンへの最初の派遣元は、キリスト教の医療団体で、クリスチャン中心のところでした。キリスト教を広めることを目的としているような節もあって…。そういうのが苦手なのでその団体をやめて独立し、自分たちで「ペシャワール会」を立ち上げたのです。
辰野
そこに至るまで、そんなに時間はかからなかったのですか。
中村
あまり敬虔なクリスチャンではなかったものですから。
辰野
ああいう社会でクリスチャンであることを表に出してしまうと、反発があったのですか。
中村
いや、そんなことはありません。金曜日にモスクで集まりがある日は、そこに行って話をすることもありました。イスラム教徒は、そのコミュニティにいれば、それに則ったことをきちんとしますし、たとえば日本に来ても「豚を食べない、酒を飲まない」といったことを守ります。人がどうであるかは置いておいて、自分の信心は守るという。他の宗教を罵倒したりなんてことはまず聞いたことがありません。
辰野
なるほど。相手を否定しないのは、すごく大事なことですね。自らを肯定するために相手を否定するという運動が、東洋、西洋の思想には垣間見られるところがあるのですが。それが今のアフガニスタンの情勢にも関わってくるというか。
中村
欧米には自分の宗教や人種的なことに対する優越意識というようなものも感じます。米兵がコーランをわざわざ射撃の的にして、現地が大変な騒ぎになったこともありました。一方、イスラム教徒には聖書を破ったり、イエスキリストを誹謗したりする行為は聞いたことがないのです。
アフガニスタンでの医療活動
辰野
ペシャワールに拠点病院を置かれて、ずっと医療活動をされているわけですけども、国境を越えてアフガニスタンまで活動を広げていかれましたね。
中村
1986年、今から20年ほど前です。まだ内戦中でした。あそこは地図に国境は書いてあるけれども、自動車で行かなければどこでも通れます(笑)。スレイマン山脈という山がありまして、そんなに高い山ではないんですが、そこを越えて、しょっちゅう行ったり来たりしていました。
辰野
アフガニスタンに行くきっかけになったのは。
中村
アフガニスタンの山の中に、非常に多くのハンセン病患者がいたことです。あの頃、ハンセン病コントロール計画という、先進国側が立てた計画がありましたが、現地にそぐわない。現地の人はハンセン病に対して、そんなに偏見を持っていませんでした。また、ハンセン病と同時に、その他の、マラリアや結核、腸チフスといった、さまざまな感染症の多発地帯でもあり、しかも入院できる施設がほとんどない。そこで、内戦が下火になったときに診療所を開設して、ハンセン病もついでに診るというか、特別扱いせずに診ることにしました。
辰野
あちらではごく普通に、ハンセン病の患者もみんなと一緒に生活しているわけですよね。
中村
例外的なところもありますが。我々がハンセン病と騒げば騒ぐほど、特別な病気と思われてしまうんです。
辰野
なるほど。
中村
それまでは「妙な、わけのわからない病気」であったものが、たたりなどの話になってきたり。そこで私たちはハンセン病を前面に出さない方針を採りました。
辰野
日本では知的障害を持った子どもたちに対しても、隔離政策が採られています。彼らを特別な組織やひとつの地域に押し込めてしまう。ネパールや東チベット辺りに行くと、障害者も健常者も一緒に生活している。それこそ泥まみれになりながら、足の不自由な子どもも一緒にいる世界が、ごく普通にある。障害者が目の前にいないという社会のほうがおかしいと気づくべきです。何人に何人かの確率で不都合な境遇にある人がいるはずなのに、そういう人が目の前にいない。1日に1回も会わないのがおかしいと、気づく必要がありますよね。
中村
そうですね。
辰野
チベットの場合は、知的障害を持つ子どもが生まれると、みんなでお祝いするらしいです。「欲を持たない子どもが生まれてきた」と。神様からの授かりものだと。
中村
なるほど。
辰野
そういうことから考えると、隔離政策も、西洋的な都合の良い合理主義のような。
中村
そうでしょうね。

ダラエヌール対岸の村での診療

カブールの診療所でハンセン病患者を診察する中村医師
「いかにして生き延びるか」 水源確保事業への挑戦
辰野
中村さんの本職である医療活動にも頭が下がる思いがするのですが、それと併行して、井戸を掘ったり、灌漑用水をつくられたりといった活動をされているのがすごいですよね。あの発想はどこからきたのですか。
中村
アフガニスタン全体がいかにして生き延びるかの問題ですから。だんだん砂漠化が進み、あと10年もしないうちに全耕作地の半分以上が消滅すると言われています。そうなると、自給自足で食べている農民のほとんどは生活が成り立たない。その人たちは死ねということなんです。なので、生き延びるためには何でも工夫してやろうという気になりますよ。「必要は何とかの母」と言いますから(笑)。
辰野
国が荒れているのは、貧困が一番の原因とお考えですか。
中村
貧困というより、自然災害、砂漠化が一番の原因です。
辰野
温暖化の影響もあるのでしょうか。
中村
温暖化ですね。
辰野
山の雪が早く溶けてしまって、保水力がなくなったんですね。
中村
1978年、ティリチ・ミールに行ったときは、雪線(※1)が3200mくらいだったんです。今は4000mになっています。わずか30年ほどの間に700〜800mは上がっています。それが一番の原因。今までヒンズーグシュの山の雪が貯水槽の役割をしていたのが、温暖化でどっと溶けるようになって。洪水は増え、乾燥地帯は広がる状態。これが一番大きいでしょうね。
辰野
僕が1969年、ヨーロッパに初めて行ってアイガー北壁を登った頃は、氷河の末端がスイスアルプスのグリンデルワルトという町までおりていて、そこでアイスクライミングの練習をしたのですが、今は標高にして500mくらい後退していると思うのです。おっしゃるように、ああいうところには木が生えていない。山そのものに保水力がないから、夏に雨が降ったら洪水がわあっと起きる。アフガニスタンみたいな地域では、必要な水がひと夏、供給できないのですよね。
中村
雪がいっぺんに溶けてしまってそうなるというわけです。標高6000〜7000mの高い場所では雪はかなり残りますが、4000mクラスの比較的低い山を水源にしている地域に被害地が多いです。
辰野
それで、思いつかれたのが井戸を掘る作業…。
中村
はじめのうちは、地下水を利用していました。井戸、それからカレーズ(※2)。
辰野
地下の用水路ですね。
中村
それが、年々水位が下がっていき、今は地下水もなくなってきているという恐るべき状態です。あとは、地表水の有効利用しかないと…。今やっているのは、無数のため池をつくること。それから、大河川から大きな用水路を引くこと。それら以外に、アフガニスタンの人々が生き延びる手立てがないのです。
辰野
なるほど。
中村
戦争も大変ですが、いずれは米軍も出て行くでしょう。みんなが怖がっているのは、戦争よりも、生きていく空間が消滅することなんです。
辰野
灌漑工事や土木作業は、中村さんご自身が独学で土木工学を勉強されたのでしょうか。
中村
そう言うと、大げさですが。どうやって水を引くのか、九州の川をあちこち見て回りました。それなりのやり方が現地にもありますし、その辺りも参考にしながら、日本のやり方と混ぜ合わせて。
辰野
蛇籠ですか。(※3)
中村
はい。よく川端柳というじゃないですか。あれはだてに植えているのではなくて、蛇籠の護岸に土のうを積んでその上に植えるんです。そうすると、石の隙間にいっぱい根が張って、籠の針金そのものはやがて朽ちてなくなっても、護岸は残るというわけなんです。
辰野
蛇籠は向こうの現地語になっているんでしょうね(笑)。
中村
そうです。うちほど大量に使っているところはないですから。
辰野
すごいですね。作業者は延べ何人くらい参加したのですか。
中村
第一期工事の13kmで延べ38万人。この1年を加えると、延べ50万人くらいになっているでしょうね。
辰野
僕はビジネスマンですから、すぐお金の計算をしてしまうのですが、日当を仮に200円としても…、1億円ですか。
中村
日当ははじめ240円でしたが。1億円になりますね。失業対策も兼ねていました。みんな食う手段がない。アフガニスタンのほとんどが農村人口なんです。しかも自給自足。だからこそ農地が荒れて難民化したわけで、故郷へ戻って工事に協力するといったって家族を養わなければならないのです。だから日当を出して働いてもらいます。働いている間は食えます。また、自分のところに水が来れば、再び農地を耕して食べ物を作り始めることができる。それで、どんどん農民が帰ってきた。
辰野
感服しました。これこそ「究極の公共事業」ですよね。
中村
しかも、蛇籠だと自分たちで保全できるわけですから。
辰野
もう少し高い給料で働けるところもあるかもしれないけど、彼らは率先して中村さんのところの仕事をするという…。
中村
自分たちの将来に関わることですから、生活者としては当然そうでしょうね。
(※1)雪線:万年雪が積もっている部分とそうでない部分の境界
(※2)カレーズ:乾燥地域で利用している地下の用水路のことを、イランではカナート、アフガニスタンやパキスタンではカレーズと呼ぶ。
(※3)蛇籠(じゃかご):竹や藤つる、鉄線などを丸く長軸に編み、中に河原石や砕石を詰めたもので、治水および護岸のための土木資材として古くから利用されてきた。一般的に屈撓性や透過性に優れ、運搬・貯蔵・撤去が容易で経済的であるという利点がある。

蛇籠を重ねた水路壁と芽を出した柳

護岸用の蛇籠を修繕する中村医師

用水路の作業現場

用水路工事のユンボ操作

用水路の試通水。水が来るというので近所の子どもたちが集まってきた。
資金の96%を現地事業に
辰野
現在の活動資金は、個人の寄付が中心なのですか。
中村
年間3億円ほどですが、100%個人です。
辰野
あえてNPO法人化しないというところにも非常に共感しています。
中村
我々が胸を張って言えるのは、手弁当形式を崩さないこと。普通、NPO法人組織にしますと、有給専従者を置かなくちゃいけない。たとえば国から5000万円もらったとするでしょ。専従者を5〜6人置くと、その給与で半分が消えてしまう。極端な例が国連組織です。たとえば何億ドルの支援をした場合に、国連職員に払うお金が半分以上。それを含めての「何億ドルの支援」なんです。その点、私たちの場合は、スタッフ1人はさすがに要るので1人だけ安月給で事務局に置いて、あとはみんなそれぞれ自発的に手弁当でやっています。組織の維持費としては、事務所の借り賃、切手代、年4回出す会報の印刷代。これだけです。あとは全部現地事業につっこんでいるんです。96%現地に使えるというのを、皆信じてくれないんですよ。
辰野
3億のお金を個人から集めて、96%が現地で使われているのは驚異的なこと。それが本来あるべき姿なのでしょうが、残念ながら、一般的ではない。
中村
ひとつのモデルになればいいかなと思います。極論かもしれませんが…最終的に日本から補給が途絶えた場合どうしようかといろいろ考えましたが、営利団体、ひとつの会社組織にして、どこかの村の請負いをして、それで食っていくという風にして続けてもいいと思っています。
辰野
それはすごくわかりやすいですね。企業は儲からないといってペナルティーが来るわけでもないし、損をしてもいいわけですから。我々が言いたいことを言えるのは、国や行政からお金をもらっていないからです。そんな中で、僕は最初、モンベル・チャレンジ・アワードを中村さんにもらっていただけるかなと心配していました。一企業である我々を認めていただき、逆に、我々が中村さんからアワードをいただいたようなものです(笑)。
中村
光栄です(笑)。
辰野
先日、ある新聞社の方とお話しする機会があり、その時に言ったのですが、どこの新聞を見ても、不祥事や改ざんなどの記事しか載っていないですよね。企業がいいことをした時は、もっとほめてあげてくれと。企業ができることは、これからいっぱいあると思います。
中村
自由な着想は、ある意味で企業にしかできません。我々が自由に動けるのは、まさに募金のお金、「すべてをアンタに任せておく」というお金があるからです。抗生物質1億円買うより栄養剤を1本打ったほうがいいよという場合にも対応できるわけです。これが国のお金ですと、医療目的のためにしか使えませんから、薬はいらないなと思っても買わないといけない。計画段階では確かにそうであっても、常に情勢は変わってくる。それに即応した動きができない。NPO法人組織にしないメリットのほうが多かったと思いますね。
願いは事業が継続されること
辰野
これから先の活動をどのようにお考えになっているのか、ビジョンをお聞かせください。
中村
私の年齢のことを考えると、あと十数年は大丈夫でしょうけど、その後は責任持てないので、その後のことが心配ですね。水路は何世代もかけて守っていくべきものです。今やろうとしているのは作業員をそこに定着させて自給自足の村を作ること、それが一番大きな課題です。
辰野
何か困っているようなことは?
中村
困っていることといえば、食糧不足。特に小麦粉の欠乏が激しく、この1年で価格が2.5倍になりました。
辰野
バイオ燃料の問題など、いろいろありますよね。食糧問題はすごく大きい。
中村
職員の給与の問題もあります。これまでの給与では、半月と家族を養えないのです。現地通貨はいずれ紙切れになるのは目に見えているから、最終的には小麦で給料を払う、昔の禄高制度をめざしています(笑)。とりあえず必要なものはカネです、はっきり言って(笑)。
辰野
次の世代を案じておられるとおっしゃっていましたが、僕も去年60歳になり、そろそろバトンタッチをしないといけない年なんです。従業員に対しては、30年後のモンベルがもし存在するとしたら、条件は2つだと言っています。1つめは、30年後もモンベルという会社が、社会にとって必要とされているかどうか。もう1つは、それが経済バランスとして自立できているかどうかです。いいことはいくらでもできるのですが、それが自己完結できないと持続性がない。ですから、中村さんがおっしゃった手弁当というのも、必ず限界があると思うんです。30年後、この2点の一方でも欠けることがあれば、モンベルは、潔く、なくなってもいいんじゃないかと僕は勝手に思っています。
中村
組織の怖いのは、「組織の存続のための存続」です。
辰野
おっしゃる通り。
中村
僕らにとっては、事業が中心。事業が遂行されるのであれば、ウチがやらなくたって、他の組織が引き取ってやるのでもいい。組織が壊滅しても、事業が継続して進行してくれればいい。「事業中心主義」に徹することができるんです。利潤をあげなくてもいいところが会社とは違います。
辰野
なるほど。
中村
今はお金が必要なのですが、組織の存続のための存続はしない、というのが方針です。用水路が必要であれば、用水路を作る。それが必要とされるのであれば引き継いでいくことをめざしています。
辰野
最後に、若い人へのメッセージをお願いします。希望の持てるような…。
中村
先が見えたこの国の後始末をするのは若い人たちです。我々の世代はボケるか死ぬか、どちらかです。若い人たちは我々年寄りの言う通りにするのではなく、自分でチャレンジをしてほしいという気がします。年寄りの小言は「今どきの若い者は」と決まっている。でも、そんな若者にしたのは我々じゃないか。昔は「若気の至り」「若いがゆえの失敗」に、もっと寛容だったと思います。ところが今、若者はマニュアルで縛りあげられており、不自由です。若い人たちがのびのびと生きていける環境をつくるのが我々の責任であって、後がどうなるかは若い人たちが見つけて、決めていってほしいと思います。
© mont-bell Co.,Ltd. All Rights Reserved.





